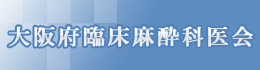- トップページ
- >
- 議事録
第44回総会・秋季学術講演会 抄録
【抄録】石川慎一先生 大阪府臨床麻酔科医会
『硬膜穿刺後頭痛と末梢神経障害性疼痛』東邦大学医学部
麻酔科学講座
医療センター大森病院 麻酔科
臨床教授 石川 慎一先生
硬膜穿刺後頭痛(post-dural puncture headache: PDPH)は、硬膜穿刺手技に伴う硬膜破綻部位からの髄液漏出が原因で生じる。多くは臥床安静や補液により1週間以内に軽快するが、症状が遷延する場合には硬膜外自家血注入(epidural blood patch: EBP)が有効である。特に硬膜外麻酔時の“不意の硬膜穿刺”では、破綻部位が大きく頭蓋内硬膜下血腫の合併にも注意が必要である。PDPHの遷延例では慢性頭痛や産後うつの発症に関与する可能性が報告されている。また「産後の肥立ちが悪い」として頭痛を見逃さないことが重要であり、再燃例や症状増悪例では鑑別診断を含めた精査を行う必要がある。したがって、PDPHに対する適切な診断と治療に加え、患者教育と説明・同意の徹底が求められる。PDPHの病態、臨床経過、治療戦略、難治例への対処について症例を解説しながら提示し、最新のガイドラインや末梢神経障害性疼痛との関わりについても概説する。
【抄録】中本達夫先生 神経障害性疼痛に対する診療
「神経障害性疼痛に対する診療 ―超音波の活用を含めてー 」関西医科大学 麻酔科学講座
関西医科大学附属病院 麻酔科・痛みセンター
教授 中本達夫 先生
ペインクリニックにおける治療対象の多くは慢性疼痛であり、近年、ICD-11において独立した疾患概念として分類がなされているものの、臨床上それぞれに対する治療法が確立したわけではなく、その中でも神経障害性疼痛は、時に難治性であり治療に難渋する。
神経障害性疼痛に対する薬物療法のターゲットとしてはカルシウムをはじめとする陽イオンチャネル、モノアミントランスポーター、TRPV1、オピオイドレセプター、GABAレセプターなど多く存在するが、現状では臨床使用可能な薬剤には限りがある。従って、Multimodal analgesiaが基本戦略となるものの、対象が高齢者などの場合、ポリファーマシーによる眠気・ふらつき・転倒など有害事象の増加にもつながることから、慎重に選択増量を行うべきである。
近年、超音波ガイド下手技によるHydroreleaseやProlotherapy, Pulsed radiofrequencyが神経障害性疼痛に対しても有効である可能性が示唆されている。薬物療法のみで十分な鎮痛が得られない場合や、局所的神経絞扼による神経障害性疼痛に対しては選択肢となる可能性がある。
さらに慢性疼痛においては神経障害性疼痛だけでなく侵害受容性疼痛や痛覚変調性疼痛が相互に関連したり、心理社会的な要因により修飾を行うものもあるため、長期化すればするほど複雑化する傾向にある。
とりわけ、破局的思考パターンを有する患者では痛みに対する認知の歪みが大きく痛み行動がより顕著となる傾向があるため、診療初期から認知行動療法的介入を行うことはメリットがあると考える。
我々の施設においても、多診療科・多職種からなる痛みセンターで集学的アプローチを実施しているものの、現状の保険診療の枠組みでは採算性が乏しい。今後の課題として、充実した慢性疼痛診療の枠組みを普及するためには、医療経済的側面からも改善が必要であると考える。







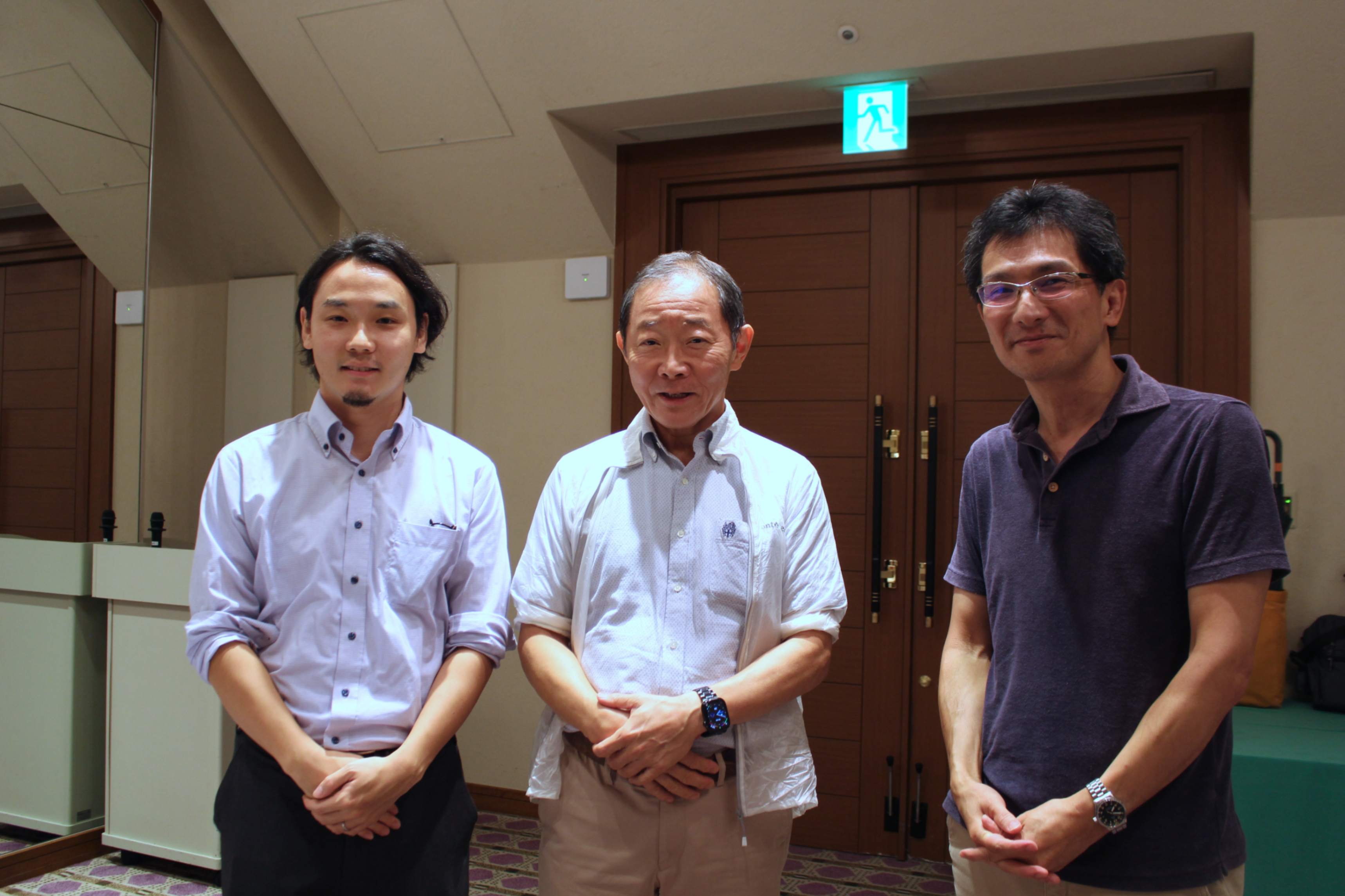
第43回総会・秋季学術講演会






第43回春季学術講演会
「慢性腰痛の治療戦略」
奈良県立医科大学 麻酔科学教室
奈良県立医科大学附属病院ペインセンター
病院教授 渡邉 惠介 先生
腰痛診療ガイドライン2019では、強く推奨されるクリニカルクエスチョン(CQ)として、①急性腰痛に対するNSAIDs、②坐骨神経痛に対するNSAIDs、③慢性腰痛に対する運動療法、④腰痛予防のための運動療法の4つが挙げられている。また、慢性腰痛に有用とされる薬剤は、合意率の高い順にSNRI、弱オピオイド、ノイロトロピン®、NSAIDs、アセトアミノフェンであった。
慢性疼痛に対しては、運動療法、心理的アプローチ、薬物治療、神経ブロック治療を組み合わせた集学的治療が推奨される。中でも運動療法は副作用がほとんどなく、運動誘発鎮痛作用(EIH)により活動性を向上させ、痛みの悪循環を改善するため、慢性腰痛治療の中心的役割を担う。
しかし、臨床の現場では、患者は完全な除痛を求めて受診する一方で、医療者は除痛ではなく運動によるADL向上を目標とする。この治療目標のずれが、良好な医師-患者関係の構築を妨げ、運動療法の導入を困難にする。例えば、腰椎手術後に痛みが残存し「怒り」を抱える患者に対しては、その感情に共感し傾聴することが重要であり、正しさを押し付けるべきではない。
共感を通じて信頼関係を築き、薬物療法やブロック治療を併用しながら運動療法を促進することが、慢性腰痛治療において極めて重要である。
「スポーツにおける膝関節傷害 ―診断から治療まで―」
関西ろうさい病院
スポーツ整形外科
部長 内田 良平 先生
スポーツにおける膝関節傷害は、“使い過ぎ”による『障害』と、比較的大きな外力で発生する『外傷』に分類されるが、その症状は、軟骨や半月板、靭帯などの関節内組織、もしくは筋腱などの関節外組織由来のものがある。有効な治療を行うには、的確な診断が重要であるが、そのためにはまずは詳細な問診、特にスポーツ傷害では、性別や年齢などの一般的な事項だけではなく、運動歴や種目、さらには受傷機転や受傷肢位、受傷時のグランドサーフェイスなども聴取する必要がある。その上で、徒手検査による理学所見の把握、的確な画像検査を行い、症状がどこから来ているかを判断することで、診断に至る。診断が確定すれば、選手の競技レベルやゴールに合わせて、治療法を選択して行く。治療法には、薬物治療、理学療法に加えて、注射や衝撃波などの保存治療と、手術治療があるが、それぞれの特徴をしっかり把握した上で行うことが非常に大切である。
本講演では、総論として、膝関節の解剖から診断及び治療について動画などで解説し、各論では、関節外のスポーツ傷害として、膝蓋腱症やオスグッド氏病について、また、膝関節内のスポーツ傷害として、離断整骨軟骨炎、膝半月損傷及び前十字靭帯損傷について、実際の症例を提示しながら、病態や診断、治療法について解説する。
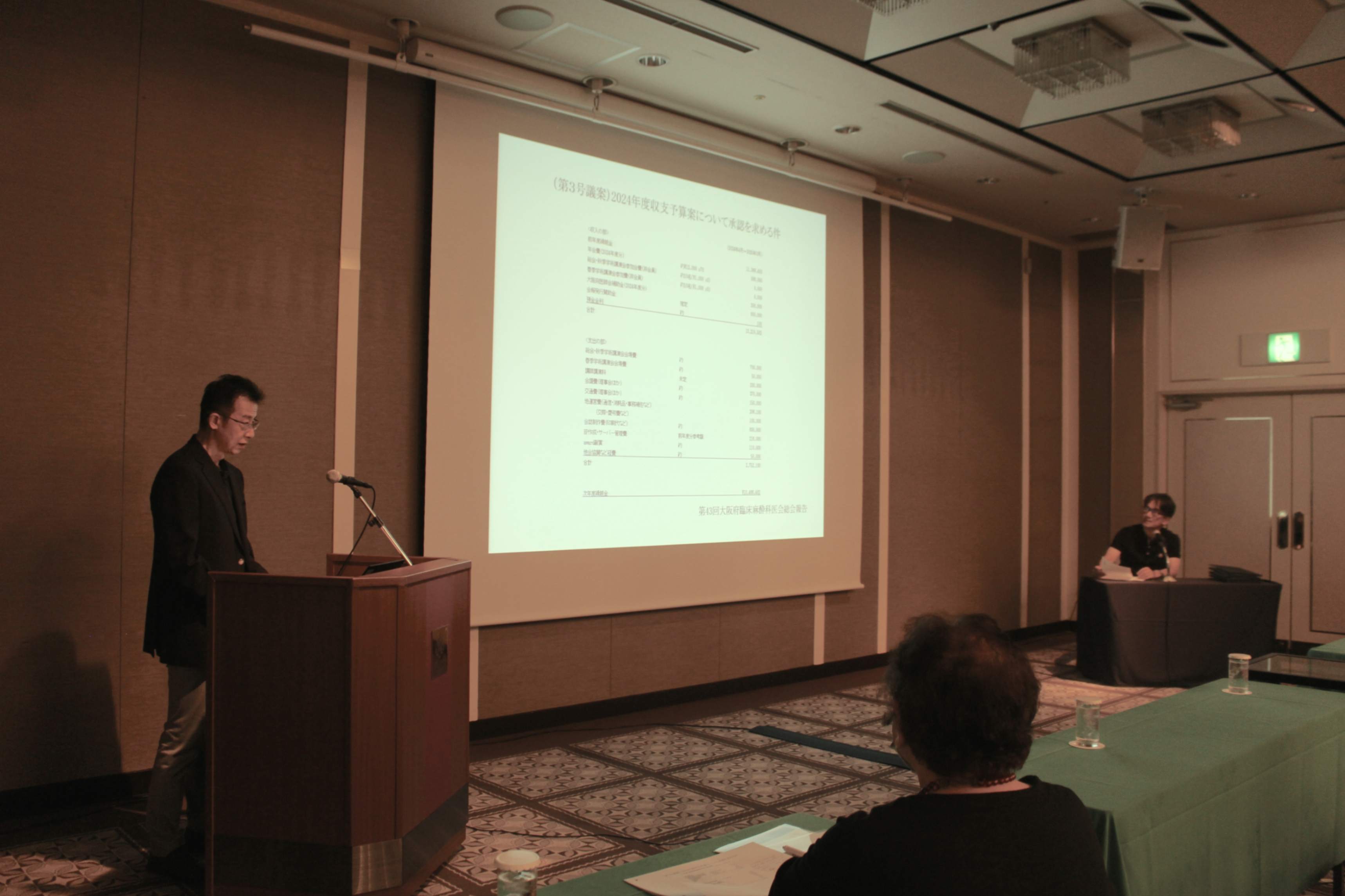









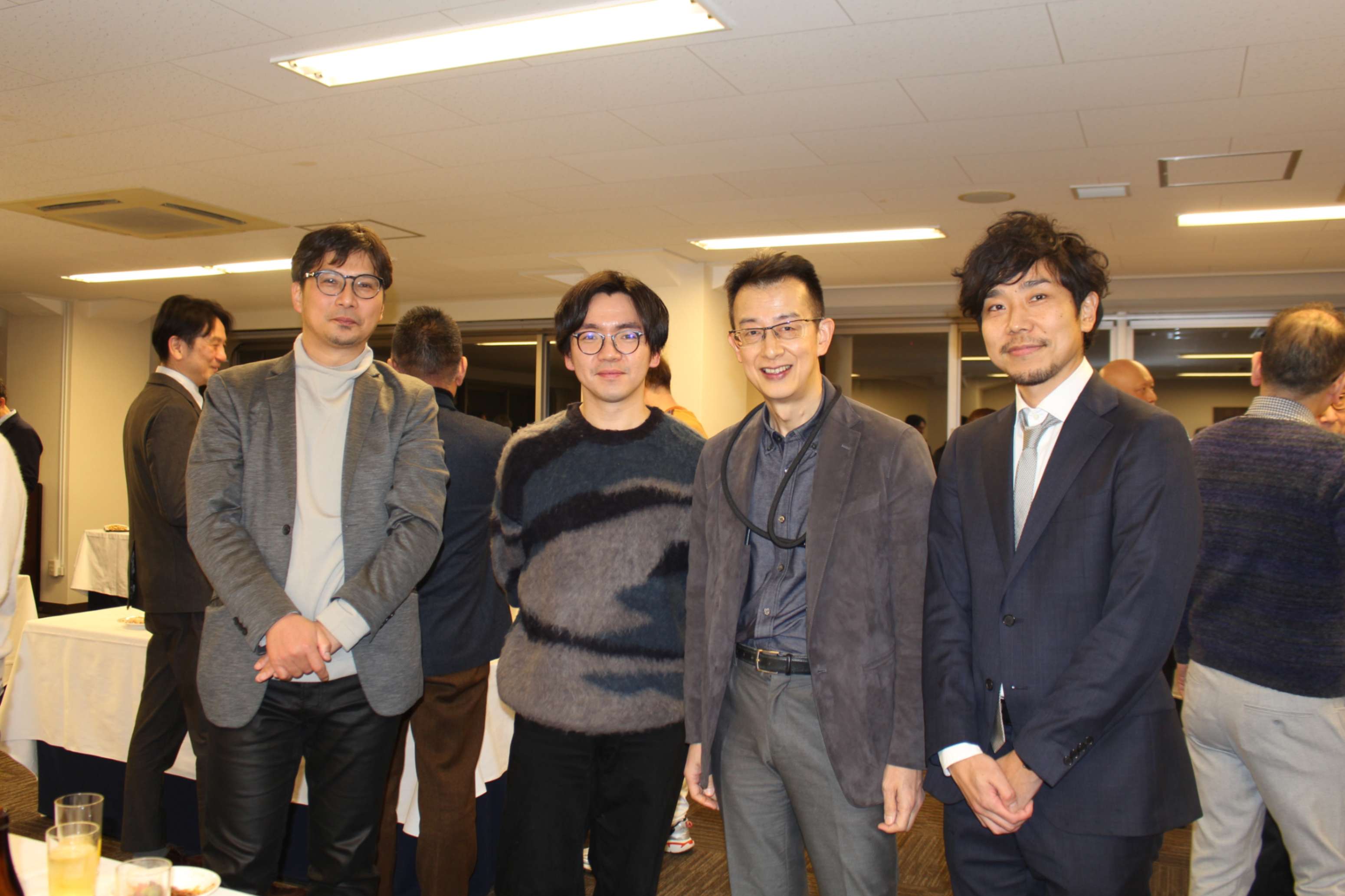


奈良県立医科大学 麻酔科学教室
奈良県立医科大学附属病院ペインセンター
病院教授 渡邉 惠介 先生
腰痛診療ガイドライン2019では、強く推奨されるクリニカルクエスチョン(CQ)として、①急性腰痛に対するNSAIDs、②坐骨神経痛に対するNSAIDs、③慢性腰痛に対する運動療法、④腰痛予防のための運動療法の4つが挙げられている。また、慢性腰痛に有用とされる薬剤は、合意率の高い順にSNRI、弱オピオイド、ノイロトロピン®、NSAIDs、アセトアミノフェンであった。
慢性疼痛に対しては、運動療法、心理的アプローチ、薬物治療、神経ブロック治療を組み合わせた集学的治療が推奨される。中でも運動療法は副作用がほとんどなく、運動誘発鎮痛作用(EIH)により活動性を向上させ、痛みの悪循環を改善するため、慢性腰痛治療の中心的役割を担う。
しかし、臨床の現場では、患者は完全な除痛を求めて受診する一方で、医療者は除痛ではなく運動によるADL向上を目標とする。この治療目標のずれが、良好な医師-患者関係の構築を妨げ、運動療法の導入を困難にする。例えば、腰椎手術後に痛みが残存し「怒り」を抱える患者に対しては、その感情に共感し傾聴することが重要であり、正しさを押し付けるべきではない。
共感を通じて信頼関係を築き、薬物療法やブロック治療を併用しながら運動療法を促進することが、慢性腰痛治療において極めて重要である。
「スポーツにおける膝関節傷害 ―診断から治療まで―」
関西ろうさい病院
スポーツ整形外科
部長 内田 良平 先生
スポーツにおける膝関節傷害は、“使い過ぎ”による『障害』と、比較的大きな外力で発生する『外傷』に分類されるが、その症状は、軟骨や半月板、靭帯などの関節内組織、もしくは筋腱などの関節外組織由来のものがある。有効な治療を行うには、的確な診断が重要であるが、そのためにはまずは詳細な問診、特にスポーツ傷害では、性別や年齢などの一般的な事項だけではなく、運動歴や種目、さらには受傷機転や受傷肢位、受傷時のグランドサーフェイスなども聴取する必要がある。その上で、徒手検査による理学所見の把握、的確な画像検査を行い、症状がどこから来ているかを判断することで、診断に至る。診断が確定すれば、選手の競技レベルやゴールに合わせて、治療法を選択して行く。治療法には、薬物治療、理学療法に加えて、注射や衝撃波などの保存治療と、手術治療があるが、それぞれの特徴をしっかり把握した上で行うことが非常に大切である。
本講演では、総論として、膝関節の解剖から診断及び治療について動画などで解説し、各論では、関節外のスポーツ傷害として、膝蓋腱症やオスグッド氏病について、また、膝関節内のスポーツ傷害として、離断整骨軟骨炎、膝半月損傷及び前十字靭帯損傷について、実際の症例を提示しながら、病態や診断、治療法について解説する。

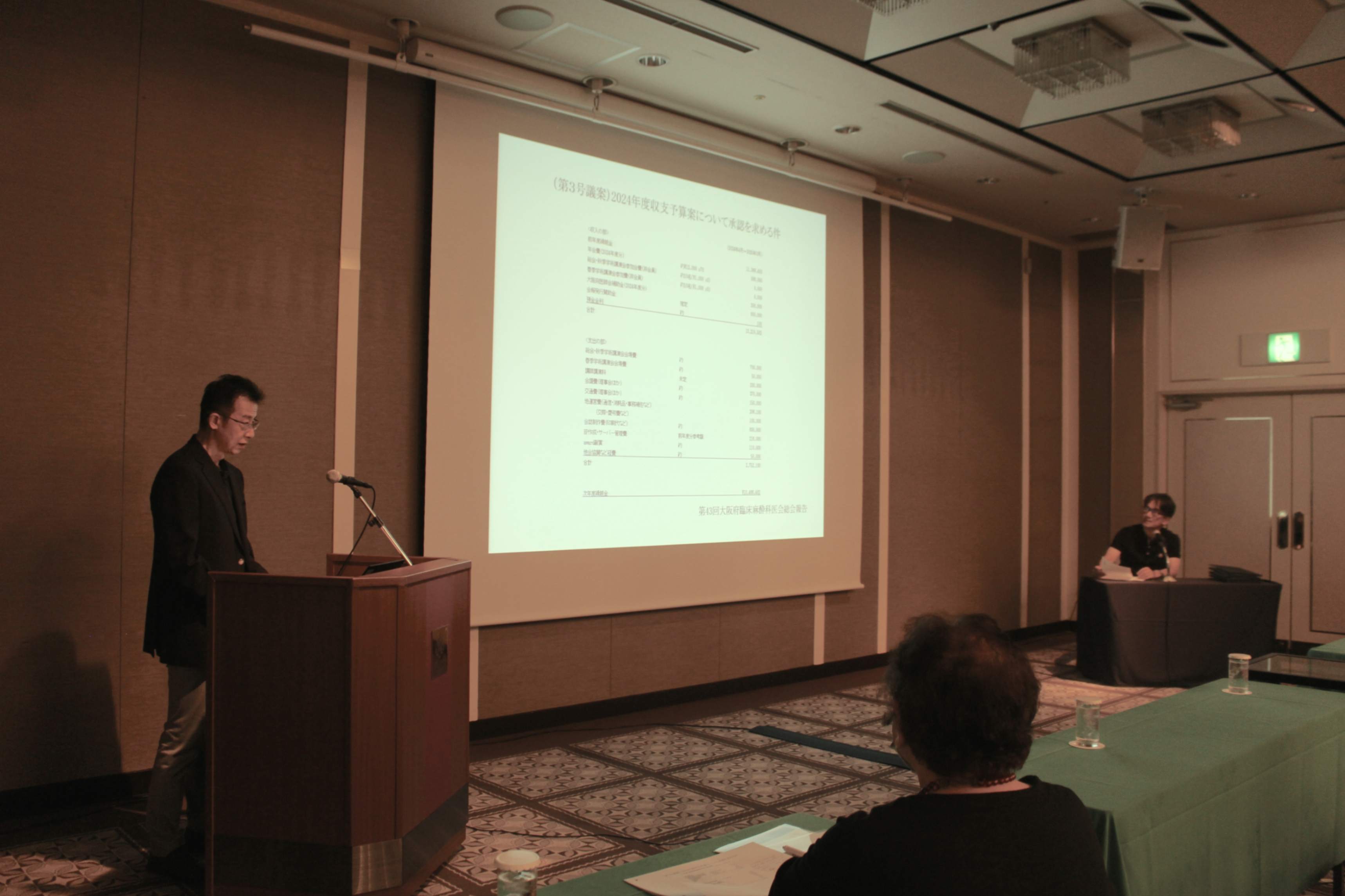









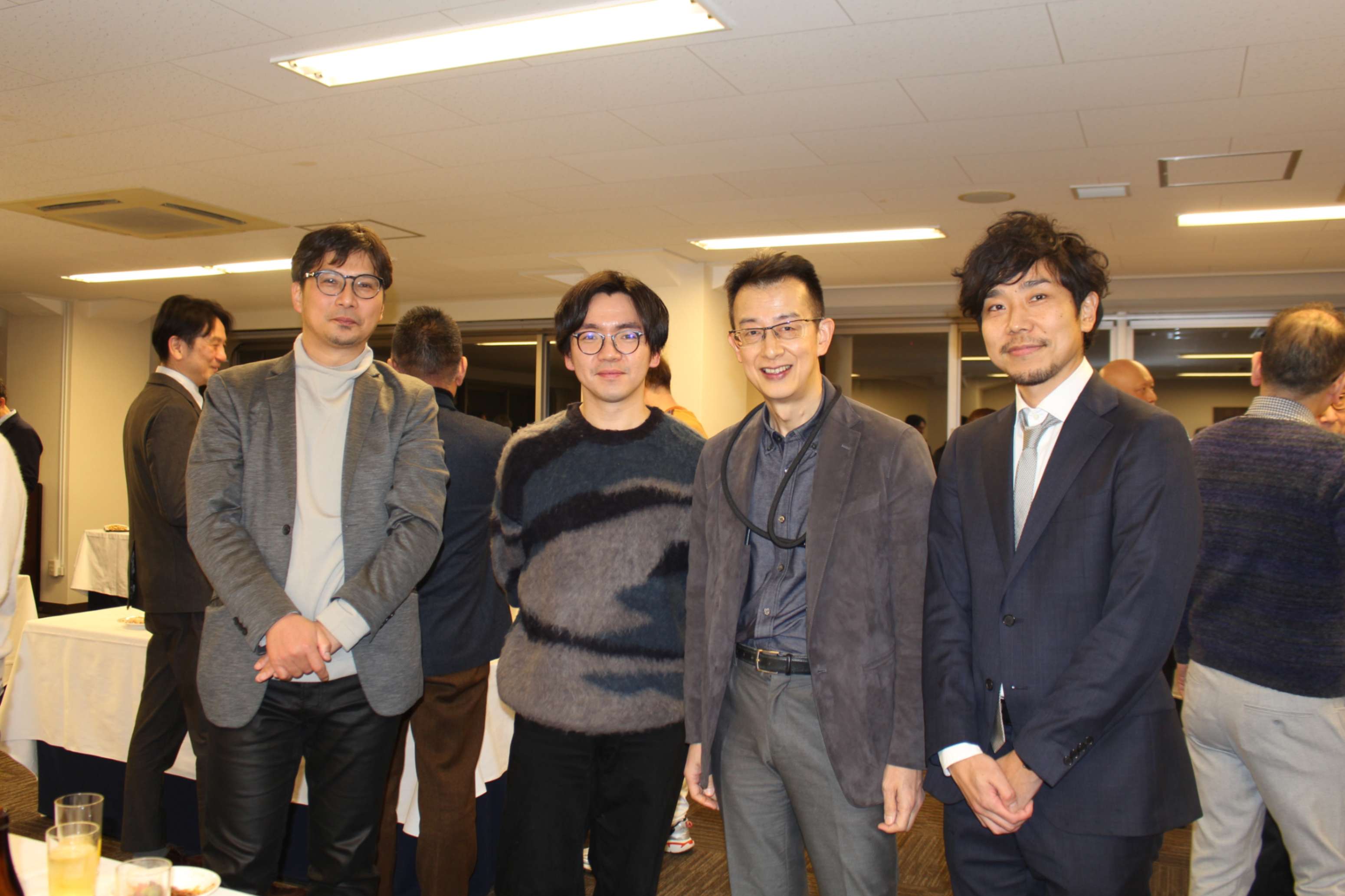


第9回 大阪府臨床麻酔科医会 Award 会長賞 奨励賞 報告
【第9回 大阪府臨床麻酔科医会 Award 会長賞 奨励賞 報告】
令和6年9月21日の第43回 総会・秋季学術講演会に於いて、下記の通り第9回大阪府臨床麻酔科医会Award会長賞・奨励賞受賞者を表彰いたしました。
【会長賞】
東邦大学医療センター大森病院
麻酔科
臨床教授 石川慎一先生
論文:
外傷性頚部症候群と脳脊髄液漏出症 診療の実際
石川 慎一
臨床整形外科 58(11) : 1325-1340, 2023
【奨励賞】
大阪医科薬科大学 麻酔科学教室 助教准 鳥井理那先生
論文:
鎮静下の椎間関節ブロックが有効であった若年性腰痛の 1例
鳥井 理那, 間嶋 望, 中尾 謙太, 南 敏明
日本ペインクリニック学会誌 31(1) 1-4, 2024
関西医科大学附属病院 麻酔科 痛みセンター 嘱託医員 中村恵梨子先生
論文:
仰臥位での腸骨筋膜下前方アプローチを用いた超音波ガイド下 L4 神経根
パルス高周波法の 1例
中村恵梨子, 旭爪章統, 中村里依子, 緒方洪輔, 上林卓彦, 中本達夫
日本ペインクリニック学会誌 31(8) 184-188, 2024
大阪大学大学院医学研究系研究科
生体統御医学講座 麻酔集中治療医学教室 医員 長田多賀子先生
論文:
下肢痛のない慢性軸性腰痛にスプリングガイドカテーテルによる経皮的硬膜
外腔癒着剥離術が著効した 1例
長田多賀子, 弓場智雄, 高橋亜矢子, 博多紗綾, 松田陽一
日本ペインクリニック学会誌 30(11) 261-265, 2023


令和6年9月21日の第43回 総会・秋季学術講演会に於いて、下記の通り第9回大阪府臨床麻酔科医会Award会長賞・奨励賞受賞者を表彰いたしました。
【会長賞】
東邦大学医療センター大森病院
麻酔科
臨床教授 石川慎一先生
論文:
外傷性頚部症候群と脳脊髄液漏出症 診療の実際
石川 慎一
臨床整形外科 58(11) : 1325-1340, 2023
【奨励賞】
大阪医科薬科大学 麻酔科学教室 助教准 鳥井理那先生
論文:
鎮静下の椎間関節ブロックが有効であった若年性腰痛の 1例
鳥井 理那, 間嶋 望, 中尾 謙太, 南 敏明
日本ペインクリニック学会誌 31(1) 1-4, 2024
関西医科大学附属病院 麻酔科 痛みセンター 嘱託医員 中村恵梨子先生
論文:
仰臥位での腸骨筋膜下前方アプローチを用いた超音波ガイド下 L4 神経根
パルス高周波法の 1例
中村恵梨子, 旭爪章統, 中村里依子, 緒方洪輔, 上林卓彦, 中本達夫
日本ペインクリニック学会誌 31(8) 184-188, 2024
大阪大学大学院医学研究系研究科
生体統御医学講座 麻酔集中治療医学教室 医員 長田多賀子先生
論文:
下肢痛のない慢性軸性腰痛にスプリングガイドカテーテルによる経皮的硬膜
外腔癒着剥離術が著効した 1例
長田多賀子, 弓場智雄, 高橋亜矢子, 博多紗綾, 松田陽一
日本ペインクリニック学会誌 30(11) 261-265, 2023


第42回春季学術講演会
「肩痛の診断と治療」
大阪公立大学大学院医学研究科 整形外科学
講師 間中 智哉 先生
肩痛が生じる頻度は、住民健診の結果によると腰痛、膝痛に続いて多く、6人に1人程度と有病率が非常に高いと報告されている。そのため、日常診療において遭遇する機会が多い。しかしながら、適切な診断や治療がされず、放置されている場合がある。肩痛の3人に1人に腱板断裂を認めるとの報告があり、有症状のまま長期間放置すると腱板断裂サイズの拡大や変性の進行が生じ、後に専門に治療している医師に紹介しても治療困難となる場合があるために注意を要する。
近年、MRI や超音波などの診断デバイスの進歩に伴い、適切な診断を行い、障害部位の病態を把握した上で適切な治療を行うことが重要となってきている。肩関節疾患の治療において、保存的加療の役割は重要で、疼痛を十分にコントロールした状態で運動療法などのリハビリテーションを行うことにより、手術的加療を行わなくても症状が改善する症例も多い。疼痛のコントロールは医師の重要な役割であるが、薬物療法、注射療法などが有効と考えられ、慢性疼痛治療薬や超音波ガイド下の関節内注射の登場により、治療の選択肢も広がっている。
本講演では、代表的な肩関節疾患の診断・病態・治療法について代表症例を交えながら解説する。
「ペインクリニックにおける椎間板内治療」
仙台ペインクリニック 院長 伊達 久 先生
痛みの治療には、薬物療法・インターベンション治療・リハビリテーション・心理的アプローチとそれらを融合した集学的治療がある。ペインクリニックが最も得意とするところは、インターベンション治療である。今回はペインクリニックで行われているインターベンション治療のうち椎間板内治療を中心に解説する。
腰部の椎間板治療の適応は、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどの他、腰痛だけで下肢症状を伴わない椎間板性腰痛の患者も対象となる。腰部脊柱管狭窄症などでは多椎間に病変が存在するため、どの椎間板が痛みに最も関与するかが不明なこともある。このようなときは複数の椎間板造影・ブロックを行って、痛みに関与すると思われる椎間を推察し、その椎間から出ている神経に対して神経根ブロックを行うことで、責任椎間の特定・治療を行うことができる。この効果が短期間の場合は、経皮的髄核摘出術なども考慮する。腰部経皮的髄核摘出術の手技にはいくつかのデバイスがあるが、患者の年齢や部位などによって使い分けている。
頚部でも同様に椎間板治療を行う。頚部の経皮的髄核摘出術のデバイスにも複数あるが、 腰部に比べて少量の摘出でも効果がみられるため使い慣れたデバイスを使うことが良いかもしれない。












大阪公立大学大学院医学研究科 整形外科学
講師 間中 智哉 先生
肩痛が生じる頻度は、住民健診の結果によると腰痛、膝痛に続いて多く、6人に1人程度と有病率が非常に高いと報告されている。そのため、日常診療において遭遇する機会が多い。しかしながら、適切な診断や治療がされず、放置されている場合がある。肩痛の3人に1人に腱板断裂を認めるとの報告があり、有症状のまま長期間放置すると腱板断裂サイズの拡大や変性の進行が生じ、後に専門に治療している医師に紹介しても治療困難となる場合があるために注意を要する。
近年、MRI や超音波などの診断デバイスの進歩に伴い、適切な診断を行い、障害部位の病態を把握した上で適切な治療を行うことが重要となってきている。肩関節疾患の治療において、保存的加療の役割は重要で、疼痛を十分にコントロールした状態で運動療法などのリハビリテーションを行うことにより、手術的加療を行わなくても症状が改善する症例も多い。疼痛のコントロールは医師の重要な役割であるが、薬物療法、注射療法などが有効と考えられ、慢性疼痛治療薬や超音波ガイド下の関節内注射の登場により、治療の選択肢も広がっている。
本講演では、代表的な肩関節疾患の診断・病態・治療法について代表症例を交えながら解説する。
「ペインクリニックにおける椎間板内治療」
仙台ペインクリニック 院長 伊達 久 先生
痛みの治療には、薬物療法・インターベンション治療・リハビリテーション・心理的アプローチとそれらを融合した集学的治療がある。ペインクリニックが最も得意とするところは、インターベンション治療である。今回はペインクリニックで行われているインターベンション治療のうち椎間板内治療を中心に解説する。
腰部の椎間板治療の適応は、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどの他、腰痛だけで下肢症状を伴わない椎間板性腰痛の患者も対象となる。腰部脊柱管狭窄症などでは多椎間に病変が存在するため、どの椎間板が痛みに最も関与するかが不明なこともある。このようなときは複数の椎間板造影・ブロックを行って、痛みに関与すると思われる椎間を推察し、その椎間から出ている神経に対して神経根ブロックを行うことで、責任椎間の特定・治療を行うことができる。この効果が短期間の場合は、経皮的髄核摘出術なども考慮する。腰部経皮的髄核摘出術の手技にはいくつかのデバイスがあるが、患者の年齢や部位などによって使い分けている。
頚部でも同様に椎間板治療を行う。頚部の経皮的髄核摘出術のデバイスにも複数あるが、 腰部に比べて少量の摘出でも効果がみられるため使い慣れたデバイスを使うことが良いかもしれない。












第42回総会・秋季学術講演会
「運動器疾患の神経障害性疼痛の治療戦略」
日本赤十字社 日本赤十字病院
麻酔科部長・ペインクリニック部長
石川 慎一 先生
運動器疾患で最も症例数が多いのは腰椎椎間板ヘルニアなどの脊椎疾患による坐骨神経痛である.椎間板内治療はIntradiscal therapyと呼ばれ,椎間板内に薬液あるいはデバイスを注入・挿入して,主に椎間板由来の腰痛あるいは神経根圧迫による下肢痛の軽減を期待する治療である.
椎間板内治療の種類は1)薬液を用いて椎間板由来の痛みの軽減やヘルニアを退縮させる椎間板内注入療法,2)高周波熱凝固装置を用いて椎間板あるいは関連する神経を熱凝固させる椎間板内高周波熱凝固治療,および3)低侵襲デバイスを用いて椎間板を変性凝固あるいは切除させる経皮的椎間板髄核摘出術,に分類できる.いずれも低侵襲であり種類によっては根治性が期待される.椎間板内治療の適応を判断するには,椎間板性腰下肢痛の存在を確認する必要がある.腰椎MRIでは,椎間板変性,椎間板ヘルニア,T2強調画像におけるHIZ(High intensity zone),Modic変性などは椎間板性腰下肢痛の可能性を示唆する所見である.椎間板造影・注入や椎間板CT所見による情報は,椎間板内治療の適応判断に有用であるが偽陽性や偽陰性を考慮する必要がある.
椎間板内治療のエビデンスに関しては,エビデンスがないデバイスが多い中で,IDET(Intradiscal electrothermal treatment)と椎間板交通枝高周波熱凝固に弱い推奨がある.経皮的椎間板髄核摘出術では,自動経皮的腰椎椎間板切除術が腰下肢痛に,DekompressorⓇが椎間板性腰痛に弱い推奨となっている.コンドリアーゼは本邦発の治療で,2019年にはエビデンスなしとなっていたが近年論文は増加しており,さらなるエビデンスの確立が期待できる.
椎間板内治療では診断から各手技にわたり,特徴をつかんで熟練することが有効性を上げるために重要でありエビデンスの構築が困難な要因の一つになっている.
今回,全内視鏡下椎間板治療による治療を含めて,腰下肢痛に対するインターベンショナル治療について解説する. 「慢性疼痛の治療・京大での試み 〜患者安全への患者参加について〜」
京都大学医学部附属病院 医療安全管理部
助教 加藤 果林 先生
慢性疼痛ガイドラインの「痛みのモデル図」に示されているように、慢性疼痛の原因には「神経障害性疼痛」「侵害受容性疼痛」「心理・社会的要因」が関与しており、慢性化すると,痛みの要因はどれか1つに起因することは少なく,いろいろな要因が複雑に絡んだ混合性疼痛(mixed pain condition)になります。
5000人を対象に行われた臨床試験では、神経障害性疼痛をお持ちの方は10.6%(10人1人)もいると報告されています。また、60歳以上の方に多いという結果になっており、高齢化社会に突入している日本では、潜在的には非常に多くの患者がいると考えられ、今後ますます増加していくことが想定されます。さらに、神経障害性疼痛は「痛みの強さ」「持続時間」ともに他の慢性疼痛よりも高い傾向にあり、日常生活に大きな影響を与えることが明らかになっています。痛みによる生活の質の低下を考えると、早急に治療されるべき疾患と考えます。治療を受ける患者・患者家族が積極的に参加し、服薬の意義を理解することで、高い治療効果が期待できます。患者・患者家族は治療を一方的に受けるのではなく、医療に参加する存在です。以前はコンプライアンスが重要視されていましたが、コンプライアンスは医療従事者から患者さんに対する一方的な指示であるのに対し、アドヒアランスは患者・患者家族自身が治療の選択や決定に携わることが特徴です。神経障害性疼痛のアドヒアレンスについて一歩踏み込んだ研究をご紹介いたします。
また、長く持続する痛みは,心理社会的な要因も関わって,病態を非常に複雑にしており、一診療科や一人の医療者での対応には限界があって当然です。
演者は京都大学医学部附属病院でペインクリニック外来医長の立場として、他部門との連携を強く推進してきました。
マインドフルネスは慢性疼痛ガイドラインでエビデンスレベル1A(行うことを強く推奨する)となっていますが、講座の受講に20~30万かかり、講座数が少ない等日本でのマインドフルネス受講のハードルは高いのが現状でした。
保険診療の枠組みの中で治療できるように、数年間の試行錯誤を経て、2022年より精神科デイケアの一環として「マインドフルネスストレス逓減法」を導入し、ペインクリニック外来患者への提供を開始しました。
苦労あり、涙あり、挫折ばかりで何度もくじけながらやっと辿りついた治療方法について概説いたします。
患者さんのご紹介を心よりお待ちしております。











日本赤十字社 日本赤十字病院
麻酔科部長・ペインクリニック部長
石川 慎一 先生
運動器疾患で最も症例数が多いのは腰椎椎間板ヘルニアなどの脊椎疾患による坐骨神経痛である.椎間板内治療はIntradiscal therapyと呼ばれ,椎間板内に薬液あるいはデバイスを注入・挿入して,主に椎間板由来の腰痛あるいは神経根圧迫による下肢痛の軽減を期待する治療である.
椎間板内治療の種類は1)薬液を用いて椎間板由来の痛みの軽減やヘルニアを退縮させる椎間板内注入療法,2)高周波熱凝固装置を用いて椎間板あるいは関連する神経を熱凝固させる椎間板内高周波熱凝固治療,および3)低侵襲デバイスを用いて椎間板を変性凝固あるいは切除させる経皮的椎間板髄核摘出術,に分類できる.いずれも低侵襲であり種類によっては根治性が期待される.椎間板内治療の適応を判断するには,椎間板性腰下肢痛の存在を確認する必要がある.腰椎MRIでは,椎間板変性,椎間板ヘルニア,T2強調画像におけるHIZ(High intensity zone),Modic変性などは椎間板性腰下肢痛の可能性を示唆する所見である.椎間板造影・注入や椎間板CT所見による情報は,椎間板内治療の適応判断に有用であるが偽陽性や偽陰性を考慮する必要がある.
椎間板内治療のエビデンスに関しては,エビデンスがないデバイスが多い中で,IDET(Intradiscal electrothermal treatment)と椎間板交通枝高周波熱凝固に弱い推奨がある.経皮的椎間板髄核摘出術では,自動経皮的腰椎椎間板切除術が腰下肢痛に,DekompressorⓇが椎間板性腰痛に弱い推奨となっている.コンドリアーゼは本邦発の治療で,2019年にはエビデンスなしとなっていたが近年論文は増加しており,さらなるエビデンスの確立が期待できる.
椎間板内治療では診断から各手技にわたり,特徴をつかんで熟練することが有効性を上げるために重要でありエビデンスの構築が困難な要因の一つになっている.
今回,全内視鏡下椎間板治療による治療を含めて,腰下肢痛に対するインターベンショナル治療について解説する. 「慢性疼痛の治療・京大での試み 〜患者安全への患者参加について〜」
京都大学医学部附属病院 医療安全管理部
助教 加藤 果林 先生
慢性疼痛ガイドラインの「痛みのモデル図」に示されているように、慢性疼痛の原因には「神経障害性疼痛」「侵害受容性疼痛」「心理・社会的要因」が関与しており、慢性化すると,痛みの要因はどれか1つに起因することは少なく,いろいろな要因が複雑に絡んだ混合性疼痛(mixed pain condition)になります。
5000人を対象に行われた臨床試験では、神経障害性疼痛をお持ちの方は10.6%(10人1人)もいると報告されています。また、60歳以上の方に多いという結果になっており、高齢化社会に突入している日本では、潜在的には非常に多くの患者がいると考えられ、今後ますます増加していくことが想定されます。さらに、神経障害性疼痛は「痛みの強さ」「持続時間」ともに他の慢性疼痛よりも高い傾向にあり、日常生活に大きな影響を与えることが明らかになっています。痛みによる生活の質の低下を考えると、早急に治療されるべき疾患と考えます。治療を受ける患者・患者家族が積極的に参加し、服薬の意義を理解することで、高い治療効果が期待できます。患者・患者家族は治療を一方的に受けるのではなく、医療に参加する存在です。以前はコンプライアンスが重要視されていましたが、コンプライアンスは医療従事者から患者さんに対する一方的な指示であるのに対し、アドヒアランスは患者・患者家族自身が治療の選択や決定に携わることが特徴です。神経障害性疼痛のアドヒアレンスについて一歩踏み込んだ研究をご紹介いたします。
また、長く持続する痛みは,心理社会的な要因も関わって,病態を非常に複雑にしており、一診療科や一人の医療者での対応には限界があって当然です。
演者は京都大学医学部附属病院でペインクリニック外来医長の立場として、他部門との連携を強く推進してきました。
マインドフルネスは慢性疼痛ガイドラインでエビデンスレベル1A(行うことを強く推奨する)となっていますが、講座の受講に20~30万かかり、講座数が少ない等日本でのマインドフルネス受講のハードルは高いのが現状でした。
保険診療の枠組みの中で治療できるように、数年間の試行錯誤を経て、2022年より精神科デイケアの一環として「マインドフルネスストレス逓減法」を導入し、ペインクリニック外来患者への提供を開始しました。
苦労あり、涙あり、挫折ばかりで何度もくじけながらやっと辿りついた治療方法について概説いたします。
患者さんのご紹介を心よりお待ちしております。











第41回春季学術講演会










「脊椎関節炎の最近の話題」
関西医科大学附属病院 リウマチ・膠原病科
科長 病院教授 尾﨑 吉郎 先生
強直性脊椎炎に代表される脊椎関節炎は「血清反応陰性脊椎関節炎」という疾患群に分類されるが、この疾患群の分類における診断基準(分類基準)と、それぞれの疾患の診断基準が別に存在し、専門に診療している医師から見てもやや煩雑である。強直性脊椎炎や乾癬性関節炎以外にも幾つかの疾患がこの血清反応陰性脊椎関節炎に分類されるが、未だに入るのか入らないのかが、しっかり確定していない疾患もあり、非専門の医師から見れば、さらにわかりにくい分野である。
それでも、近年は分類基準が整理されつつあり、またCTやMRI、関節超音波などの診断デバイスの進歩から、診断までの期間が格段に短縮されている。日常診療における進歩は診断の範囲のみではなく、治療に用いることができる薬剤の進歩も著しい。
従来は進行を遅らせることは至難の業であったが、生物学的製剤などの登場は、患者さんのADL維持を可能にしている。さらに、疼痛管理においてもNSAIDs以外にオピオイド製剤が使用できるようになったことで、これらの疾患に罹患する患者さんのQOLの改善に大きく寄与している。
近年、大きく変化した血清反応陰性脊椎関節炎に関して、概略ではあるが提示させていただく。
「慢性疼痛の病態とリハビリテーション~疼痛感作からPost COVID-19まで〜」
神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科
教授 松原 貴子 先生
慢性疼痛は,典型的には3か月以上または通常の治癒期間を超えて持続する痛みと定義され,その病態には疼痛感作が関与し,心理社会的因子の影響を受けるとされている(慢性疼痛診療ガイドライン,2021)。運動器の慢性疼痛は,COVID-19罹患後症状(Post COVID-19 condition)のひとつであり,広範性疼痛に次いで頚部痛,そして肩・腰・膝痛などの訴えが多く,この病態にも疼痛感作や心理社会的因子の関与が示唆されている。このような慢性疼痛に対し,各国の慢性疼痛診療ガイドラインでは,運動と患者教育がfirst-lineに位置付けられている。
運動は,“Exercise is the best medicine(運動は最善の薬)”として,commonな慢性二次性疼痛だけでなく,痛覚変調性疼痛(nociplastic pain)に分類されるような慢性一次性疼痛にも奏効するポテンシャルを有している。その効果メカニズムとして,運動誘発性鎮痛(exercise-induced hypoalgesia: EIH)や脳報酬作用が根拠となっている。しかしながら,ただ運動するだけでは効果量は小さく,また運動負荷が過剰となれば逆に痛みを惹起する可能性があり,運動バリアによる制限も起こりうる。よって,運動は“Exercise is a good medicine”ではあるが最善の治療法とまでは言えず,そこが運動療法の限界であり今後の課題ともいえる。
その対策として必要になるのが,reassuranceや治療過程における共同意思決定を可能とする患者教育のような行動変容アプローチとの併用であり,それによって効果の底上げが期待される。また,疼痛を緩和し運動導入・継続をサポートする薬物療法やインターベンション治療などの生物医学的治療は,運動療法とともに慢性疼痛治療の両輪をなす治療法であり,多大な効果が期待できる。
本講演では,慢性疼痛の病態として疼痛感作に着目し,現在増加傾向にあるPost COVID-19疼痛の話題にも触れながら,運動療法の有効性と課題を整理し他治療との併用の意義と相補的効能について考えながら,慢性疼痛治療に対するリハビリテーションの最善策について議論を深めたい。
第41回総会・秋季学術講演会の抄録
「手・前腕・肘の痛みと整形外科的アプローチ」
JCHO大阪病院 副院長 兼 手外科・外傷センター長 島田 幸造 先生痛みとは、A unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage.(国際疼痛学会)と定義されるように、Tissue damageに伴う不快な感覚、ただし必ずしもTissue damageがあるとは限らず、あったとしても組織学的には治癒している場合もあることで我々は混乱する。整形外科的にはまずそのあるべきTissue damageを検索し、治療することから始める。そのためには、1)どこが痛むのか(骨?関節?筋肉?皮膚?)2)どんな時に痛むのか(安静時?運動時?朝?夜中?使い過ぎた後?)3)どうすると楽になるのか(挙上?冷やす?温める?動かす?NSAIDs?)といったことを検討し、病態を解明し治療に繋げる。
関節やその近傍に起因する痛みとして、野球肘やテニス肘、腱鞘炎などオーバーユース障害では、それが骨軟骨障害なのか、靭帯や筋腱など軟部組織障害なのかを検討し、障害部位を修復、あるいは除去して再建することで治癒させ、疼痛を改善させる。血流障害や神経性の疼痛については、外傷性神経血管損傷、急性および慢性循環障害に伴う神経因性疼痛、手根管症候群を代表とする絞扼性神経障害など多岐にわたるが、それぞれの病態を理解すれば治療法方針も明確になる。循環障害であれば血行再建や筋膜切開などによる循環動態の改善、外傷性神経損傷では偽神経腫を形成させないような修復、絞扼性神経障害であれば圧迫部位の切離開放により改善が図れる。長期間の疼痛は中枢感作を生じ難治性となるケースがあり、我々はそれを予防し、改善することを目指している。
u 関節の痛み、関節付近の痛み
Ø 野球肘、テニス肘(ゴルフ肘)
u 腱鞘炎
Ø 屈筋腱腱鞘炎(バネ指など)、ドゥ・ケルバン病
u コンパートメント症候群
Ø 急性(骨折後)、慢性(CECS)
u 神経の痛み
Ø 神経損傷、絞扼性神経障害(手根管症候群)
上記を中心に、実際の手術例を供覧して我々のアプローチを紹介する。
「 今考えたい日本の便秘診療 ~最近の新しい治療 strategy~ 」
兵庫医科大学 内視鏡センター・消化器内科学講座 准教授 富田 寿彦 先生慢性便秘症はありふれた疾患で、診療科を問わず、多くの医師が自身の経験に基づいて診断や治療をしてきた疾患である。慢性便秘患者の多くは医療機関を受診せずに自ら生活習慣や市販薬を内服していたりする場合が多い。これまでの多くの研究から著しく患者の日常生活や労働生産性を損ない、QOL を低下させることが知らされているため、適切に治療すべき疾患であるといえよう。昨今は COVID-19 環境下でのストレスや運動不足の影響で、これまで以上に便通異常を訴える患者を診療する機会が増加したと感じる先生方も多いのではないだろうか。超高齢化社会を迎えた本邦において、慢性便秘患者は増加の一途をたどっている。特に高齢者は併存疾患や処方薬、食事量や運動量が減少するなどの生活環境の変化に加え、腸管運動に関与する様々な因子が便秘症の要因となる。さらに便秘症は生命予後への影響も示唆されており、高齢者では特に治療すべき疾患と考える。
ここ数年で慢性便秘症の薬物治療の選択肢が広がり、患者個々の病態に応じた治療が可能になってきたことで、QOLの高い治療を提供することが可能になっている。既存薬含め各種薬剤の特徴や留意事項を踏まえて適切に選択することは重要であり、有効性・安全性の両面から治療を進めて行くことは重要である。そこで本セミナーでは、消化器内科医師の立場から慢性便秘の薬物治療における薬剤選択時の留意点と治療の意義、さらに新規治療薬であるエロビキシバットの使用上のポイントについて概説する。
第41回総会・秋季学術講演会










第40回春季学術講演会
矢部充英先生抄録
オピオイドを使うときのPitfall~安全に使用するために大阪市立大学大学院医学研究科 麻酔科学講座 講師
大阪市立大学医学部附属病院 麻酔科・ペインクリニック科
矢部充英 先生
オピオイド鎮痛薬は手術麻酔のみならず、日常臨床においてもその強力な鎮痛作用を活かして様々な場面で活用されている。
欧米に比べてその消費量が少ないと言われてきた本邦においても近年、慢性疼痛に対してオピオイド鎮痛薬の適応拡大が図られ、現在数種の強オピオイドが使用可能となっている。
また、がん患者においては、治療と診断の技術が進むにつれて治療成績が向上し、「がんサバイバー」が増え「がん性疼痛」の臨床経過が変化してきた。
オピオイド鎮痛薬は使い方によっては精神と行動の著しい変化、依存性や耐性を生ずる可能性があり、使用する際には十分な痛みの評価と適応について慎重に判断されるべきである。にもかかわらず、その不適切な使用により、離脱困難などの転帰をとるケースがしばしば見受けられることも事実である。
本講演会では私の経験した症例を提示しながらオピオイド鎮痛薬の適切な使用について理解を深め、共に議論できればと考えている。
林田賢治 先生抄録
肩関節拘縮と腱板断裂 ~長く続く肩の痛み~第二大阪警察病院 副院長
整形外科 部長 林田賢治 先生
肩の痛みが長く続くと、夜間痛がおこり睡眠が妨げられたり、強い肩こりが起こるので頭痛や頸部痛が引き起こされやすい。その結果、気分不良、イライラ感、全身倦怠感が起こりやすくQOL低下を引き起こすことが多い。長く続く肩の痛みを起こす代表的な疾患として、肩関節拘縮、腱板断裂、変形性肩関節症、インピンジメント症候群があげられる。今回の講演では、4つの疾患を鑑別するための診察の勧め方を紹介し、保存的治療および外科的治療の実際を解説する。
鑑別するための理学所見として、まず可動域の評価がある。正常可動域を獲得するためには、1)関節構造が正常であること、2)関節を稼働するための筋力があること、3)軟部組織(筋や靭帯)の正常な長さがあること、が必要である。したがって可動域の異常を伴う場合は、上記に何らかの異常を起こしている可能性がある。可動域には自動可動域と他動(介助)可動域があり、この両者の評価が重要である。また、関節可動域は個体差が大きいので、左右の比較が診断上重要である。筋抵抗テストも重要な評価項目である。肩関節は骨組織による支持が少なく、関節安定性の多くを軟部組織(筋、靭帯)で行われている。筋抵抗テストはその中の筋肉の評価を行うもので、主に外転筋(棘上筋テスト)、外旋筋(棘下筋テスト)、内旋筋(内旋抵抗テスト、Napoleonテスト)の評価を行っている。上記の診察の組み合わせで、おおよその病変を予想する(表)。日常診療では、これら一連の診察は5分程度で終われるので、先生方の日々の診療に活かせていただければ幸いである。
この臨床診断をもとに検査を行うが、単純X線、MRIが肩関節では有用である。単純X線検査では、関節破壊の有無、肩峰の形態および骨棘形成、骨頭の移動等を評価する。MRIは非常に情報が多く、関節水腫(肩関節、肩鎖関節、肩峰下滑液包)の有無、腱の評価、筋委縮や脂肪変性の有無なども評価可能である。
肩関節疾患の治療の基本は保存的治療で、どの疾患でも、まず可動域訓練や薬物、注射療法を行い、除痛と可動域獲得する。その後に、筋力訓練等の機能訓練を行い機能回復と再発防止を目指す。しかし、筋断裂や関節破壊などの構造上の破綻を起こしている場合は、保存的治療の限界で、外科的治療の適応となる。
表
| 可動域 制限 |
臥位で 改善 |
SSP テスト |
外旋 テスト |
内旋 テスト |
Napoleon テスト |
|
| 拘縮肩 | あり | なし | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 不可 |
| 腱板断裂 (~3cm) | なし | なし | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 |
| 腱板断裂 (3cm~) | あり | あり | 陽性 | 陽性 | SSC 大断裂 |
SSC断裂 |
| 肩OA | あり | なし | 不定 | 不定 | 不定 | 不定 |
| インピンジメント症候群 | なし | なし | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
第40回春季学術講演会